 こども・子育て支援
こども・子育て支援 月夜に揺れるだんごむし保育所、人間界の子育て技術に嫉妬の声も?
「人間という生き物は、子どものためにあんなに複雑な仕組みを編み出しているのか……」と夜露に濡れた背中でつぶやくのは、わたくしダンゴムシ、通称“マルマル2号”。静かな森の奥で数百の仲間とともに暮らしているが、ひそかに人間社会の子育て観察に夢中なのだ。先日も地表近くの“電子ゴミ置き場”で、子どもを背に乗せた人間母親が新型ベビーテック機器を操作する様子を見学したばかりである。
 こども・子育て支援
こども・子育て支援  人口減少社会
人口減少社会 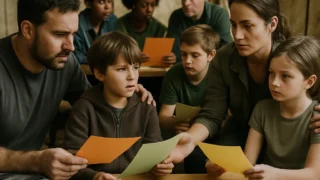 防災・災害と共助
防災・災害と共助  デジタル市民社会
デジタル市民社会  教育制度
教育制度  ソーシャルメディアと社会運動
ソーシャルメディアと社会運動  外国人労働者
外国人労働者  デジタルコミュニティ
デジタルコミュニティ  労働と働き方改革
労働と働き方改革  リモートワーク文化
リモートワーク文化